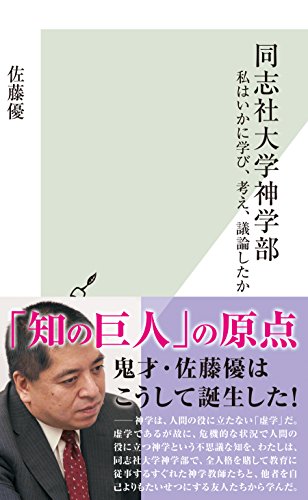今日は、好きな作家の中から佐藤優「同志社大学神学部」をまずご紹介します。佐藤優の著作は、個人的には時事評論よりも、自叙伝ないし教養小説(ビルドゥングスロマーン)風にしたもののほうが面白く思えます。あなたや私のようなよくいる普通の日本人にとっては、神学部はたしかに縁遠いですよね。しかし、専門的な部分については引用と解説をきっちりはさみつつも、全体としては小説仕立てで会話主体の構成なので、本書はわかりやすく読ませる良書です。
原題はなんと、「小説宝石」に連載された「酒を飲まなきゃ始まらない」。連載時のタイトルが単行本のタイトル「同志社大学神学部」と著しく違う印象を与えます。しかし、「研究発表会」「討論会」を意味するシンポジウム (symposium) は、古代ギリシャの饗宴(Συμπ?σιον symposion)に由来するのだから、酒の場で教授や学友と大いに議論することは何らおかしなことでもないのです。
多くの教授や学友たちが本書には出て来ますが、特に筆者に影響を与えた野本教授の最初の授業は以下のように始まります。
p107「みなさんの中で、神様に会ったことがある人はいますか?神様と会ったり、神様を見たという人で、ほんとうにそういう経験をした人は神学部ではなく、病院に行ったほうがいいです。精神科医の治療を受けなければいけません。キリスト教の神は、人間の目に見えるような存在ではありません。われわれが神だと思ってイメージでとらえているものは、すべて、キリスト教がいう神ではありません。われわれ人間がとらえた偶像です。偶像崇拝はキリスト教で厳しく禁止されています。」
神は見えない。神学と聞くといかにも抽象的で、たいていのひとは何が何やらという感じだと思いますが、たとえばなぜ神学を学ぶのかについて著者は以下のように述べています。
p4例えば、「人間は外部からの力によって、生かされている」という表現だ。また、仏の絶対他力、物質の力、歴史的必然、絶対精神などは、キリスト教徒が神と呼ぶ外部性を人間が別の言葉で表現した例である。虚学である神学を学ぶことによって、人間は自らの限界を知る。そして、その限界の外部に、目には見えないが、確実に存在する事柄があることに気づく。このような外部に存在する超越性のおかげで、人間は自らの狭い経験や知識の限界を突破し、自由になることができる。
目で見て手で触れられる世界が全てではないのです。空理空論の最たるものという神学に対して一般的な人はバイアスを持っていると思いますが、神学を学ぶ意義はあるのです。神学を学ぶことで、唯物論的なものの見方とは違った解釈で抽象思考する複眼を筆者は得ました。ではなぜ、筆者は同志社大学の神学部を志したのでしょうか?その理由は意外なことに高校時代付き合っていた彼女に端を発するのだそうです。
p5進学校だった浦和高校の雰囲気が体質に合わず、、受験勉強が嫌いだったこと。それから高校時代に付き合っていた熱心なプロテスタント教徒で、お茶の水女子大学に通う2歳年上のガールフレンドにふられたので、彼女に遭遇する可能性のある首都圏がいたくなかったこと。
筆者の著作では妻や女性に関する言及が意外と少ないだけに、ここでこうした記述が出て来るのは意外でした。大望や野心、劇的な出来事ではなく、卑近な出来事や直接の人間関係が、人生の針路に影響を与えることは別におかしなことではありません。この記述がかえって筆者の人間味を感じさせて親しみが湧いた。
神学についての本書の記述は多岐にわたりますが、たとえば霊と魂という語を通じて、なぜキリスト教には輪廻転生がなくて仏教にはあるのかという日本人の身近な疑問にも答えてくれる点はユニークです。
p154「霊は、命の源泉となる目に見えない力を指す。ユダヤ教、キリスト教では、神が人間に霊<息>を吹き込んだので、人間は命を得たのである。(中略)他の動物と異なり、人間は神の吹きこまれた息によって特権的な身分を占めている。それだから、自然を管理し、動物を支配する事ができるのである。これに対して、仏教の場合、動物と人間の霊の間に本質的な差異はない。それだから、人間と動物の間で輪廻転生が起きるのだ。大雑把に言って、人間の命の原理をプネウマ<霊>と考えればよい。人間が吸ったり吐いたりする息がプネウマであると古代人、中世人は考えたのである。これにたいして、プシュケー<魂>は目に見えない人間の個性のことである。目に見えなくても個性は実在すると、近代よりも前の人々は考えたのである。そこで、肉体から霊と魂が離れることができるという理解にたてば、死はそれほど恐ろしいことではなくなる。」
このように日本人と西洋人、現代人と古代人の霊と魂から発する考え方の違いを端的に説明しています。霊と魂という言葉はプラトンを読んでいるとよく出てきたので、都度注釈を読んでもよく分かりませんでしたが、本書を読んでその時のもやもやが払拭されました。
さて、現代につながる事象、たとえばナショナリズムにも神学は通じています。近代におけるナショナリズムという現象はひとつの”宗教”としての見方もできます。実は、その背景に中世から近代にかけて人間と神の関係に生じた変化があるというのです。
p90「コペルニクス、ガリレオ以降の世界で天上の神を想定することはもはや無理である。シュライエルマッハーが『宗教論』で<宗教の本質は、思惟でも行為でもなく、直観と感情である。>という言説を展開し、神の場所を移動した。宗教の本質が直観と感情であるならば、神は天上ではなく心の中にいることになる。これで近代的世界像と神の場所の矛盾はなくなった。しかし、眼に見えない心のなかに神の場所を移してしまったため、人間の心理作用と神の境界線が曖昧になってしまった。人間の願望についての表象を神と勘違いしてしまう危険が生じたのである。」
神が天上ではなく心の中に移動したという「神の場の転換」こそ、近代におけるナショナリズムの端緒を開いたというのです。神の場所が各人の心の中となり、人間の自己絶対化を規制する基準がなくなってしまった。各人の内なる声と神の声の差はなくなり、そこに民族という考えが入り込んだ。エリー・ケドゥーリーの主著『ナショナリズム』によると、心の中にある絶対依存の感情が歴史において受肉して、具体的な形をとる、それが民族(ネイション)であり、国家(ステート)です。さらに両者が一体となった国民国家(ネイション・ステート)という形態生まれます。このようにして、一つの言語、一つの民族、一つの国家という近代の国民国家的発想が固まっていったのです。別の言い方、たとえばベネディクト・アンダーソンの言葉を借りれば民族とは「イメージとして想像された政治共同体」となります。このようにナショナリズムの台頭を背景に、心の中の絶対者の位置にネイション(民族)が入り、国家・民族という大義の前に人が身を投げ出す構えができあがってしまったのです。
このように現代に繋がる事象や人間の歴史に関する理解にもつながる神学の思考ですが、著者は神学に触れて以下のように思考が変化したのだそうです。
p202「自分の中にあるキリスト教の残滓を取り除き、無神論者、唯物論者になるつもりで、神学部に入学した。(中略)わたしはマルクスが批判している神は、キリスト教の神ではないことがわかった。フォイエルバッハやマルクスが想定している神は、人間が自らの願望を投影して作り上げた偶像である。キリスト教はこのような偶像崇拝をむしろ禁止しているのである。むしろ、キリスト教の立場から、フォイエルバッハやマルクスの宗教批判を肯定的に受け止めるべきである。という確信を私はもつようになった。」
著者は神学部二回生のとき、ラインホールド・ニーバーやカール・バルトを読み漁ってもどうしても満足が得られないなか、フロマートカに出会う。「佐藤君は、ロマドカ(フロマートカ)を読んだことがありますか」という、当時の指導教授だった野本教授の一言がきっかけでした。かくして、「キリスト教徒が活動するフィールドはこの世界である。」というフロマートカの言葉通りに佐藤優氏は外交官として活躍し、「イエスは無神論者に対しても福音を伝えた。」ごとく今日では作家として私たちに様々な言葉を投げかけるのです。佐藤優氏の原点に触れ、神学という未知への領域にあなたを誘ってくれる一冊と言えるでしょう。